行徳揉み
行徳の神輿渡御に欠かせないのが、「行徳揉み」と呼ばれる独自の揉み方です。
渡御の始めと終わり、あるいは途中要所要所で「さし」「放り受け」「地すり」という独特の揉み方を披露します。

さし
神輿を片手で頭上高くさし上げ
神輿を中心として時計回りに回転する

放り受け
神輿を水平に放り上げて
さらしを巻いた両手首で受け止める
神輿が宙に浮いている間に2回手をたたく

地すり
神輿を地面すれすれまで下げ
神輿を中心に時計回りに回転する
これらは、天の神様(さし)や地の神様(地すり)へ五穀豊穣を感謝し、放り受けは神様を喜ばせるという意味があるそうです。
本来はさし→放り受け→地すり→さし→放り受けの順番が正式とされ、渡御を始める時はこの順番で揉みますが、近年は、渡御の途中に入れる場合は地すり→さし→放り受けの順番で揉み、工程を減らして担ぎ手の負担を減らしているそうです。
行徳のお隣・浦安の祭りでも同じような揉み方が行われます。
「擦り」「揉み」「差し」「放り」で構成され、合わせて「地すり」と呼ぶようです。
「地すり」を行う祭りは東京・江東区にも2~3あり、昔から湾岸一帯に伝わった担ぎ方ではないかと考えられているそうです。
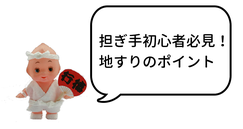
| 「地すり」の揉み方 |
|
地すりの基本形は、担ぎ手が神輿に背を向け外側を向いて行います。 頭を下げて前かがみとなり、中腰の態勢のまま両手を後ろに伸ばし、手のひらを担ぎ棒の下深くに入れ、膝の裏に棒を押し付けながら、後ろ手で引っ張り上げるようにします。 担ぎ手全員この姿勢が揃ったら、音頭取りの「まわれ!」の掛け声のもと、ずり足で時計回りにゆっくりと一回転します。
神輿の胴を支える人は、低い半身の態勢で頭を前の担ぎ手の背中(腰上)につけ、腰を中心として体全体を神輿の胴に押し付け、右手を後ろ手にして引っ張り上げるようにします。 このとき、できるだけ手のひらを神輿の胴の台座下奥深くに入れて、上に引っ張り上げるのがコツだとか。力の入れ具合が特に難しい場所だそうです。 |
では実際に動画で見てみましょう。
基本的な行徳揉み
「さし」「放り受け」「地すり」の基本的な行徳揉みです。
町ごとに掛け声や揉み方が若干異なります。
中には「放り受け」を行わない祭り(上妙典の祭礼)もあります。
江戸前担ぎの行徳揉み
江戸前担ぎを行う新井と相之川の地すりでは、担ぎ手が神輿の方(内側)を向き、担ぎ棒を膝の前で持ちます。これは浦安の地すりと同じ形ですが、行徳では浦安のように地すりで神輿を揺らしたり、さして回るときに担ぎ棒を叩いたりはしません。そこが行徳ならではの揉みのこだわりだそうです。
例外となるのが下妙典の獅子頭の地すりです。こちらは浦安と同じように内側を向いて獅子頭を激しく揺らします。

|
昔の行徳の人たちは、農業や漁業に従事し足腰や腕力が強い人が多かったそうです。
体力的に一番きついとされる「地すり」では、「こぶし一つ分の地面ぎりぎりまで神輿を下げる」ことが重要で、これができないと神輿の音頭取りに怒られたそうです。 |
|
近年では、なかなかそこまで下げた地すりは見られなくなりましたが、地すりや放り受けは町ごとの個性が特に表れやすい部分です。 ぜひ注目して見てみてください。 |

行徳仕様の担ぎ棒
行徳の神輿の担ぎ棒には、地すりのときに指を引っ掛けやすいように、下部に溝が彫ってあるものが多いです。
地すりは後ろ手で担ぎ棒を持つため、これがあると無いとでは持ちやすさが断然違うとか。
ただし担ぐときはこの溝が肩にあたり痛くなるので、深すぎず浅すぎずを加減して彫ってあるそうです。
神輿を見る際は、ぜひチェックしてみてください。


